118番の日(1月18日)は、日本において海上保安庁が2010年(平成22年)12月に制定し、翌2011年(平成23年)から実施されるようになった記念日です。この特別な日は、海上保安庁が運用する緊急通報用電話番号「118番」を一般の人々に広く知ってもらうことを目的としています。なお、「118番」は2000年(平成12年)5月1日に運用を開始し、10周年目に記念日とされました。
この記念日の背景には、「118番」が他の緊急通報用電話番号である「110番」や「119番」に比べて知名度が低いという事実があります。そのため、「118番」の存在を広く浸透させ、一般の人々にも利用されることを促進することが、記念日の目的とされています。
「118番」は緊急時に海上での事故や災害、救助が必要な状況で利用される電話番号です。この番号を知っていることは、海上での安全や救助活動において極めて重要です。しかし、他の緊急通報用電話番号と比較して、知名度が低いことから、この日は「118番」の周知活動が一層行われる日となっています。
初めての118番の日では、海上保安庁運用司令センターが報道関係者に公開され、その存在や機能が広く知られるようになりました。この「通信指令室」に相当する運用司令センターは、緊急時における迅速な対応を担当しており、その活動が一般の人々にも理解されることで、「118番」の信頼性や効果が向上することが期待されます。
海上保安庁は、この記念日を通じて、国民に対して海上での安全意識を高め、緊急時には適切な手段で連絡を取ることができるよう啓発活動を行っています。特に、海上での事故や災害において時間の重要性が極めて高いため、迅速かつ正確な情報提供が求められます。
この記念日は、一般の人々にとっては「118番」を知り、覚えておくことの大切さを再確認する機会となっています。また、報道を通じて海上保安庁の役割や緊急通報の手段について理解を深め、安全な社会の構築に寄与しています。







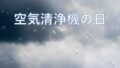
コメント