1878年(明治11年)2月20日、「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定されました。この日は、日本において「旅券」という用語が初めて法令上で使用された歴史的な日です。それ以前は、「海外行御印章」とか「海外行免状」と呼ばれていましたが、この規則の制定によって、より一般的で明確な「旅券」という言葉が定着しました。
この日、1878年2月20日に制定された「海外旅券規則」は、日本の外務省によって布達されました。この規則は、国内から海外へ渡航する際に必要な文書や手続きについて定めたものでした。当時の日本は明治時代の初期にあり、急速な近代化の進展とともに、国際社会との交流が増大していました。このような時代背景の中で、海外渡航者の増加に伴い、より効率的で適切な手続きを確立する必要が生じたのです。
それまでの「海外行御印章」と「海外行免状」は、渡航者が外国での身分や権利を証明するための文書でしたが、制度が不統一であったり、その有効性に疑問符がつくこともありました。このため、より明確で信頼性の高い旅券制度が必要とされていました。
「海外旅券規則」の制定により、「旅券」という文書が定義づけられました。旅券は、国籍や身分を証明し、国外での滞在や渡航を容易にするための公式な文書として位置づけられました。この規則の下、旅券の発行手続きや有効期間、使用条件などが明確に定められ、国内外の行政機関や外交使節団との連携が図られました。
日本が「旅券」という用語を法令上で初めて使用したこの日は、国際的な交流と外交関係の発展にとって重要な一歩でした。旅券の制度化は、個々の国民の権利と自由を保護し、国家間の信頼関係を築く上で重要な役割を果たしました。
1998年(平成10年)には、この歴史的な出来事を記念して、「旅券の日」という記念日が制定されました。外務省が制定したこの日は、旅券の制度が日本の近代国家建設に果たした役割を称え、国民の国際交流への意識を高める機会として位置付けられています。
「旅券の日」は、日本の外交史や国際社会との関わり合いを振り返り、未来に向けてより良い国際関係を築くための機会でもあります。旅券は、個々の国民の自由を保障し、国家間の協力や信頼を深める重要なツールであり、その制度化は日本が国際社会においてより活発に参画し、発展していくための基盤となりました。
このように、「旅券の日」は、日本の国際的な地位や関係性を理解し、その重要性を再確認する機会として、毎年2月20日に国民によって祝われています。





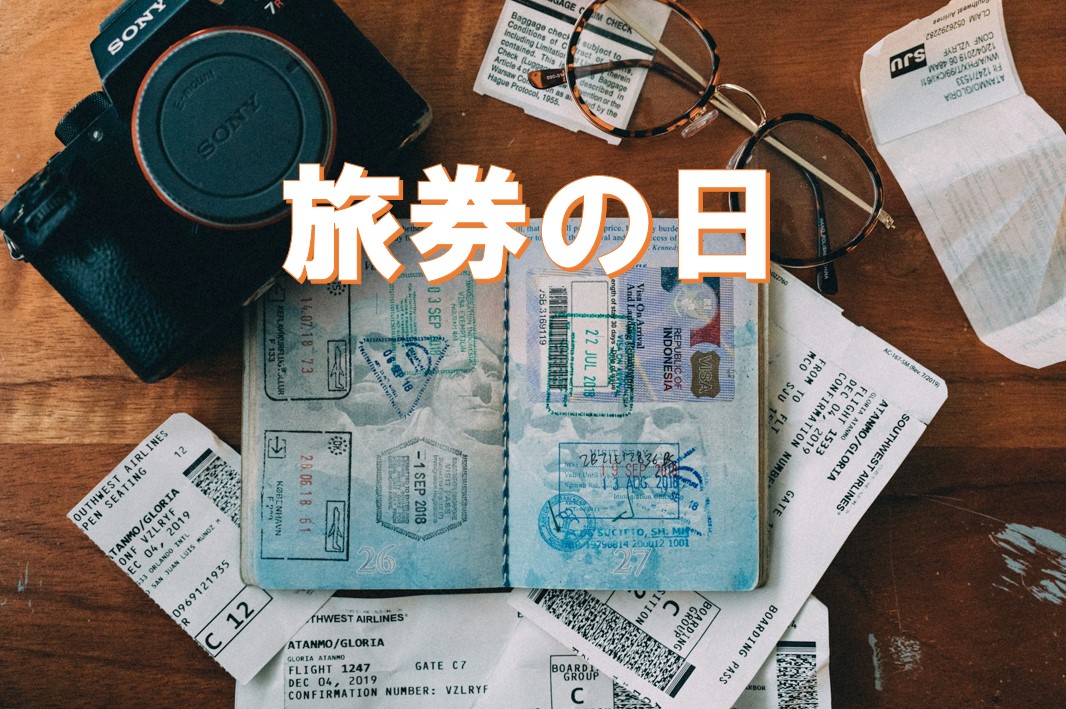

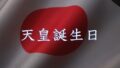
コメント