クリスマスツリーの日(12月7日)は、日本において初めてクリスマスツリーが飾られたとされる日を記念する日です。1886年(明治19年)のこの日、横浜の明治屋にて、日本初のクリスマスツリーが飾られたとされています。このツリーは、外国人船員を対象としたもので、日本におけるクリスマスの歴史の一部を刻んでいます。
明治屋は、1885年(明治18年)に横浜・万代町に創業された企業で、現在は東京都中央区京橋に本社を構え、食料品・和洋酒類の小売・輸出入、船舶に対する納入業を営む小売業者です。その創業地である横浜でのクリスマスツリーの飾り付けが、日本におけるクリスマスの伝来を象徴しています。
ただし、この日よりも前にも日本でクリスマスツリーが飾られていた可能性があります。クリスマスの文化や習慣が外国から持ち込まれ、徐々に日本に浸透していった経緯が考えられます。クリスマスツリーはキリスト教圏の伝統であり、外国との交流や文化の交換によって、日本にも広まっていったと考えられています。
1900年(明治33年)、明治屋が東京・銀座に進出すると、銀座でのクリスマス飾りが一般的になりました。同時期には、神戸でクリスマス用品の生産が始まり、日本国内でのクリスマスの普及が進んでいきました。これにより、クリスマスは徐々に日本全体で広く認知され、祝われるようになりました。
1928年(昭和3年)、朝日新聞の記事において、「クリスマスは今や日本の年中行事となり、サンタクロースは立派に日本の子供のものに」との記述があり、クリスマスが日本の年中行事として確立されていたことがうかがえます。これは、日本社会がクリスマスを一つの祝祭として受け入れ、親しんでいく過程を示しています。
クリスマスは日本において、家族や友人との交流を重視したイベントとして広く親しまれています。クリスマスツリーやイルミネーション、クリスマスケーキなどが飾られ、プレゼントを贈り交換する習慣が根付いています。クリスマスは、冬の訪れと共に心温まる季節のひとつとして、日本中で楽しみにされています。
このように、日本におけるクリスマスの歴史は外国との交流や文化の導入、地域ごとの発展など様々な要素が絡み合いながら形成されてきました。クリスマスツリーの日は、その歴史の一部を象徴し、日本がクリスマスを祝う文化を築いていく過程を物語っています。





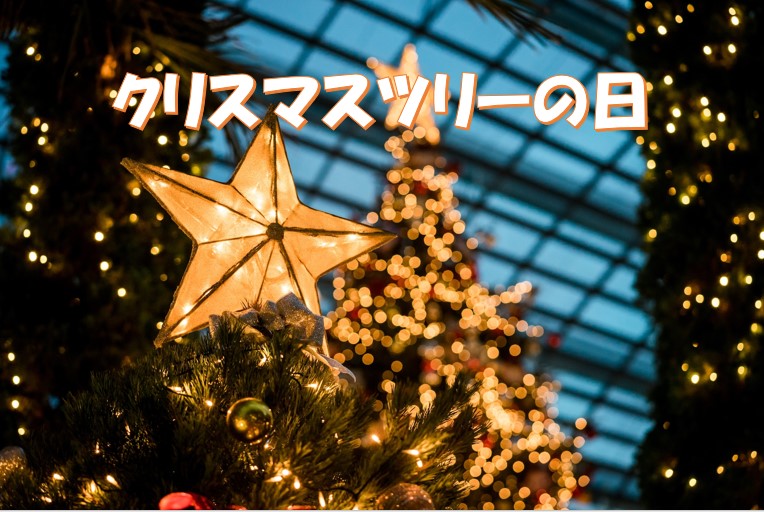


コメント