年賀郵便特別扱いは、日本における新年の挨拶の伝統的な手段として確立され、その歴史は古く奈良時代まで遡ります。新年の年始回りという行事が奈良時代から存在し、平安時代には貴族や公家にも広まりました。挨拶が難しい遠方などへの代替手段として、書状による年始挨拶が行われるようになりました。
年賀状の特別扱いが具体的に指定局で開始されたのは1899年(明治32年)であり、その後1905年(明治38年)には全局での特別取扱いが開始され、翌1906年(明治39年)には正式に制度化されました。この特別扱い期間は12月15日から12月25日までで、この期間に投函された年賀状は翌年の元日・1月1日に届く仕組みとなっています。
挨拶文化が時代とともに変化していく中で、江戸時代には飛脚が書状を運ぶようになり、年賀状もその一環として広まりました。しかし、近年では若い世代を中心に、携帯電話やスマートフォンを用いたメールやソーシャルメディアを通じて新年の挨拶を行う人々も増加しています。
年賀状の作成方法も時代とともに変遷しています。かつては手書きが一般的でしたが、簡易印刷機やプリントゴッコの導入により、印刷による作成が一般的になりました。更に、現代ではパソコンやスマートフォンを活用したデザインや印刷が一般的となり、個性的で洗練された年賀状が多く作られています。
なお、年賀ハガキを通常のハガキとして扱いたい場合は、特別扱いを避けるためにハガキ表面の料額印面の下部にある「年賀」の文字を二重線などで消すことが一般的です。
年賀状は単なる通信手段を超えて、日本の伝統や文化を反映した大切な儀式となっています。特に特別扱い期間中に届く年賀状は、新年を迎える喜びや感謝の気持ちが込められ、多くの人々にとって心温まる瞬間となっています。





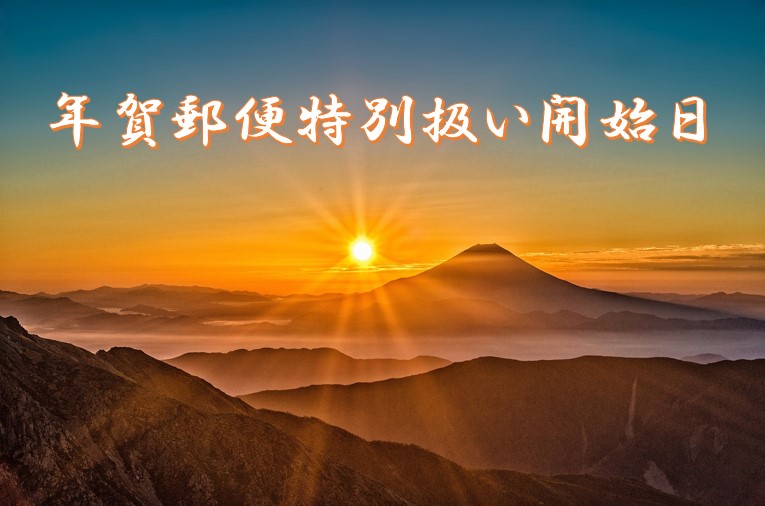


コメント